表 紙(P.1)


□ 警察の事情聴取70回(P.3-6)
□ 意見書―産科医療補償制度についてー(P.7-13)
□ 検察に告ぐ(P.14-14)
□ 『開業医から見た産科医療補償制度』(P.15-18)
□ 『院内助産所に対する法的見解』(P.19-25)
□ 『広尾事件と大野事件』(P.26-36)
□ 四禁掟の黄昏(P.28-42)
□ 上申書―胎児減数手術に関する法的見解ー(P.37-39)
□ 法の欠陥(P.40-43
Ⅰ、数日前の読売新聞:
富山県射水市民病院元外科部長が家族の要望により末期がん患者の人工呼吸器を外した事件で富山県警はこの元外科部長を殺人容疑で書類送検
2年前の事件である。今になって書類送検とは。この記事で驚いたのは警察の事情聴取が70回におよんだと載っていたことである。
これは任意捜査であろう。強制捜査が70回も許されていいはずがない。任意だからいくらでも行うのである。彼らは仕事でやっているのかもしれないが、医師はそれに付き合っていられない。こうした捜査は明らかに憲法違反、人権侵害である。医師は拒否すべきだったのである。
憲法第38条: 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
憲法第31条: 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
ここには警察のこのような考え方がある。犯罪者はうそをつく。何度も同じ質問を繰り返しているうちにうそではつじつまが合わない事項が出てくる。そこを突いてゆけば真実にたどりつける。いわゆる"落とす"というやつである。質問は医師が「私が殺しました」と言うまで続けるのである。医師は最後までそう言わなかった。そう思っていないからである。
医療行為に係わることにおいての捜査でこういう手法が適当だろうか?起こった事実ははっきりしている。隠し様もないのである。
Ⅱ、別の事例:
平成19年9月、山口県医師会生涯教育セミナー104回の特別講演「異状死体届出義務の変遷」と題された講演の中で、紹介された症例の1つにこのようなものがあった。脳障害を負った小児、気管切開を行い、気管カニューレが設置されていた。入院中、夜間、気管カニューレの設置が緩み外れた。看護師が気付き主治医に連絡、医師は蘇生したが結局児は死亡。医師はこれを異状死として警察に届けた。その後の取調べの為この医師の警察への出頭が30回に及んだ。警察は「先生が看護師に気管カニューレの固定をしっかりする事を言い忘れたのでしょう」と言う。医師は「看護師が気管カニューレの固定をしっかりするのは当たり前の事だから、特に言い忘れた訳ではない」と主張。警察は医師が自分の過失を認めない為、繰り返し尋問を続ける。医師の過失とする自供が欲しいのである。だが医師は認めない。認めれば尋問は終わるのだが認めない為延々として続くのである。この死を異状死として警察に届けたが為このような事態に追い込まれた訳である。これは警察官の認識不足から来たものである。患者の異状死届け、即ち医師の業務上過失致死疑いの届け、と勘違いしている。
Ⅲ、鹿児島選挙違反冤罪事件:
その地区の住民全員が捜査の対象になり踏み絵まで行わせた事件が明るみに出た。これも同じ事である。「私は選挙違反をしました」と自供するまで尋問を続けるのである。これも警察官の認識不足から来たものである。あるいは知っていて任意捜査であるのに強制捜査と見せかけたのか。民衆も無知だったのであろう。憲法38条、31条という法の存在を知らなかった。裁判所命令の令状を見せろと言えばよかったのだ。もし本当に令状があれば逮捕しているはずである。令状なんか無かった。無いからこそ任意の出頭を繰り替えさせたのである。
これら3つの悲劇は警察の違法捜査から来たものである。いや違法捜査では無かったのだ。これは任意で行われた捜査であるから違法性はない。その事は警察も認識済みであろう。ただ警察が「これは任意捜査ですから、出頭するか否かはあなたの自由です」などと親切に言わず、単に「警察へ出頭して下さい」と言ったのである。言われた方は「はい、分かりました」と言ってしまう。だが民衆の無知を非難すべきではないであろう。憲法の条文を知り、その意図する内容まで熟知している人の方がマニアックなのだ。
Ⅳ、第2回山口県警察医研修会
今年の3月、山大法医学と県警捜査1課主催による警察医に対する研修会が開催された。 講演内容から法医と県警では異状死の定義の仕方が若干異なるという印象を受けた。そこで私は講演を行った捜査1課長に質問をしてみた。
私の質問:「私は産婦人科医です。お産での母親の死亡は今の講義の警察の定義では異状死に入らない。しかし法医の定義では異状死に入る。では質問ですが、お産で母親が死亡した時に、警察に異状死の届出をしたら警察は捜査をするのか。つまり業務上過失致死を立件するための捜査対象になるのか」
検視官:「警察としてはこのような事案を認知したら、捜査の対象になるであろう」 私:「憲法38条に守られているという保証がなければ異状死の届出ができないと思うが」
検視官:「私の立場からは、ご協力をいただきたいと申し上げるしかない」
このやりとりから判るように警察は法医学会による異状死の定義や医師法21条と憲法38条31条との関係をよく理解しているとは思えないのです。ただ「捜査にご協力を」と言っているのでこれは任意捜査であることはよく解っている
Ⅴ、こういう状況で我々に打つ手はあるのか
異状死の届けあるいはその他の死で医師が業務上過失致死罪の嫌疑をかけられたとき、それが冤罪であると自ら確信出来ていれば、私は以下のような方法があると思う。とにかく70回も聴取されてはかなわないのです。
方法:
1、憲法38条を前面に出す。
2、警察からの質問は書面で箇条書きにさせる。それに書面で答える。
3、重複した質問事項にはそれは何月何日にすでに回答済みとし、対応しない。
4、特に医師法21条による異状死届けである場合には、届出時に自分の業務上過失は存在しないと言明する。この言明によりその後、自分の業務上過失致死罪を立証する為に行われる捜査への協力拒否は正当となる。
日本産科婦人科学会 理事長 吉村 泰典 殿
日本産婦人科医会 会長 寺尾 俊彦 殿
学会及び医会は過酷な産科医療紛争による会員の疲弊を鑑み、当制度を立ち上げて下さいました事と感謝しております。第1の目的は患者救済であることは間違いありませんが、第2の目的として現状の産婦人科医の救済も含んでいることも疑いありません。後者の救済のあり方について会員の立場からの意見を述べさせて頂きます。訴訟を起こされる事が前提としての医療側からの発言ですので医師を守る立場としての思考となります。
第2の目的達成の為にはこの制度は"かなめ"となる2つの要素が欠如していると思われます。欠如している2つの要素とは①これが紛争の終点となること、②当事者の責任の追求とを切り離すこと、の2点です。
Ⅰ、紛争の終点にするには
紛争の終点無しではこの制度は医師にとっては何の意味もない。
患者の訴権を奪うことは出来ないというのがこれが盛り込めない理由だという事ですが、こうした事は一般の民事訴訟、例えば離婚訴訟等では極当たり前に行なわれている事である。お金だけ受け取らせて念書にサインを貰わないのは間が抜けているとしか言いようがない。「これだけ頂いたのだからこれできれいに終わりにしましょう」あるいは「こんな金額じゃ納得できない。サインしない」そうした駆け引きは当然ある。念書も貰わず、ただ金品だけ渡すのは、これはただのプレゼントに過ぎない。
被保険者は医師である。当然保険料を請求するのも医師である。医師は「これで紛争の終点にする」という患者の念書が無ければ保険料請求はしないと言う事は違法ではない。その主張は当然の権利なのである。念書を書くのが嫌で補償金が出ない患者には訴訟を起こす権利は当然残っている。どこにも違法性は無い。訴訟を起こす権利は患者にある。その権利を破棄する代わりに医師から医師が懸けていた補償金を貰う。ここに何も違法性は生じない。
Ⅱ、補償金の支給条件
(イ)、小児科医の補償対象であるという診断書。(ロ)、産科医の補償該当分娩であったという証明書。この2通の書類のみ整えば補償金は支給されることとする。補償金の支給に関して調査機関の報告書は必要としない。
いや、もし大変、奇特な医師であり念書なしで保険請求を書いて上げますよというならそれは本人の自由である。それを止めることは出来ない。何人もそれを止めることが出来ないのと同様、学会、医会そして当制度委員会も医師が患者から念書を取ることを禁じる事は出来ない。
Ⅲ、当事者の責任の追求とを切り離すには
前項の(イ)と(ロ)を満足させれば補償金は支払われることにする。支払いに関して調査機関の報告はその効力を持たせない。
この制度で患者の救済と事故の原因究明の一石二鳥を狙おうとするのは虫が良すぎるのである。この制度は救済処置のみに徹するべきである。これを利用し患者の救済、医師の救済、学問の追及、民事及び刑事責任の裁定等、一石四鳥を狙っても無に帰すであろう。そううまく行くものではない。
Ⅳ、事故原因追求はこれと別個の機関を駆動すべきである。
日本産婦人科学会が今年2月29日に発表した「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等のあり方」に関する見解と要望の中の精神に示されていると同様に、脳性麻痺の原因追及に関しても、これを厚生労働省の下部組織におくべきではない。理由はその見解と要望に述べてある事と同様で、①事故に関わった医療提供者が真実を語れない。②調査報告書の内容が不正確となる可能性が生じる。③医療全般の萎縮を招くことにより医療の進歩が遅れるのみならず、医療の提供者と受給者の信頼関係を損ない社会に悪影響を及ぼす。と言った付帯事項が生じるからである。事故原因追求は別箇の独立した機関を設置すべきである。
更に私が最も危惧する流れの構図は以下のようなものである。日本医療機能評価機構が事故原因を調査する。事故調査委員会の報告書が当該医療機関のみでなく患者家族にも渡される。この制度が適用になった家族を弁護士が探し出し、訪問する。弁護士は「報告書を鑑定させてくれないか」と言う。「いや鑑定だけだから、そして鑑定料は無料ですから」と言う。鑑定の結果、勝てそうな物件を選び「お宅の場合は3000万で泣き寝入りすることはないですよ。1億は下らないです。裁判したらどうですか。お手伝いしますよ」と言う。結果、訴訟件数は増加する。
Ⅴ、クライアント契約
こうした流れを食い止めるため、事故原因追求は日本医療機能評価機構と別の機関に置く。 例えば医会支部内に事故報告事務局を設置する。報告書は医会会員全員とクライアント契約を交わした県弁護士の事務所内の金庫室に保管する。この金庫室には支部長他医会の数人の事故調査委員しか入る事が出来ない。ここで事故内容を審議する。結果は事件番号で本部に報告し実名は出さない。本部で統計処理をする。こうする事によって会員は安心して本音を報告する事が出来る。
Ⅵ、判定
審査員は臨床に携わっている産婦人科医で構成されるべきである。専門性は必要である。他科の医師や医師以外の委員を判定に介入させるべきではない。その科の常識的な医療水準を熟知している事が必要である。
判定は①該当事件は当時の医療常識から逸脱した医療過誤が認められる。②医療常識内の出来事である。の2つにどちらかとし、審査内容は公開しない。これは例えば大学受験の答案用紙の審査のようなもので、合格か不合格かの発表でよい。医療に100点満点中100点をとるような答案は存在しない。95点の高得点を取ってもマイナス5点の原因は何かと追求することは出来るのである。医療裁判はこのマイナス点の洗い出しに過ぎないのである。大学入試の合否の際に合格した者、不合格だった者の答案用紙を公表すれば不合格を出した生徒の予備校の先生は自分の生徒と合格した生徒の答案用紙をつき合わせ、採点の付け方に不服を申したてる事になる。特に論文形式ではそんな事をすれば収拾がつかなくなる。ここはこの大学の審査員が決定した合否事実を公表するだけでよい。
予備校の先生は模範解答を作成できるかもしれない。しかし本番でこの通りの答案を書ける生徒はいるだろうか。一発勝負の試験なのだ、当然緊張もある。医療行為も1つ1つが本番で真剣勝負であろう。予備校の先生が後になって模範解答を示すのは簡単である。自分は100点満点中100点の医療を行っていると豪語する医師にこれ以上の進歩は望めない。彼の学問はそれでストップしている。学問の進歩の為にマイナス5点の追及は必要である。だがそれは大学入試の合否と距離を置いたレベルで行なわれなくてはならない。
Ⅳ、患者家族への説明
患者家族は該当医師のみでなく、この調査にあたった医会支部内の事故調査委員会から調査結果を聞くことが出来る。回答は①医療過誤が認められる。②医療常識内の出来事である。の2つにどちらかとし、審査内容は公開しない。
調査委員会はこの先生は合格ですよと家族に伝えればいいのである。もし不合格でしたと伝えた場合でも、この結果は今後の医療に必ず反映されますと説明する。患者がそれを不服として訴訟を起こすならそれは自由である。ただこの答案用紙は渡さない。訴訟を起こし3000万のところが1億になるかもしれないし、1000万あるいは敗訴になるかもしれない。補償金を受け取るか、それを拒否して訴訟するかの患者の選択権は保障されている。
Ⅶ、最後に
この補償制度にこれが①紛争の終点となること、そして②当事者の責任の追求とを分離すること、の2点を盛り込んで頂きたい。具体的には患者側から念書を取る事を禁止しない、機能評価委員会の調査を拒否できる権利を認める。この2つを認める事は、この補償制度第一目的である患者救済を侵害する事にはならない。
医師法21条を振りかざし医師を罪に陥れようとする時代は終わった。考えてもみよ、これは医師が診療行為中に犯したミスを追及するに過ぎない。医師に殺意がなくて患者が死んでしまった、そういう過失致死が立証出来るか否かそれのみに有効な手段であろう。これに頼っていては計画的犯罪、殺す意思があり医療機関内で行われた犯罪は見逃してしまうことになる。医師が計画的に行なった殺人を暴く為には何が必要か。異状死届けが出されていようが出されていなかろうが、プロの感で臭いと感じたらさぐりを入れなくてはならない。
今建設中の医療事故調査委員会など本物の犯罪の立証に関しては無力であろう。警察はこれを信用すべきではない。犯罪に関しては犯罪捜査のプロがその任にあたるべきである。過失致死という事象のみに限定した捜査でなく、病死として届けられた死体でも犯罪の疑いのあるものには手をのばす。こうした姿勢がなくては社会に対する責務が果たせているとは言えないのである。
手術に失敗したら懲役1年。患者家族の心情を慮り検察は医師に刑を求刑する。刑が確定し執行される事に何の意味があるだろうか。法の解釈をめぐり法廷で論争することに何の意味があるだろうか。異状死という用語の定義など言葉の遊びに見えてくる。
新聞など医療界の聖域が守られたと報道しているが、それは違う。医療施設であろうと犯罪が疑われる場所には踏み込んで行かなくてはならない。ただ捜査起訴において医師法21条違反を旗頭にするのは稚拙すぎるのである。
産科医療補償制度開始
本年1月から産科医療補償制度がスタートした。出産一時金が3万円上乗せされ、その分を医療機関が保険会社に保険金として納入する。該当患者へは計3000万円の補償金が支払われる。医療機関は当補償制度内に設置された調査機関より事故原因分析調査を受ける。なお医療機関のこの制度への加入は任意である。
利点は3つ上げられる。①患者側にとっては訴訟手続き無しで自動的に補償金が給付されること、②医師側にとっては訴訟が激減すること、③厚生労働省側にとっては産科医療を自省の監視下に置くことが出来るようになること。
さて①の患者側への利点については問題ないであろう。そして、③産科医療を厚生労働省の監視下に置くことが出来るは確かであろう。だが、②医師側にとっては"訴訟が激減する"は確かであろうか?
これが紛争の終点となる確約がない
アメリカでは無過失補償を貰えば訴訟はできないし、訴訟をするなら無過失補償は貰えない。どちらを選択するかは患者の自由である。ニュージーランドでは医療過誤は法律で、決まった額の補償を受け訴訟は出来ない。日本においてニュージーランド形式を採用するのは法的に無理がある。しかしアメリカ形式は今の日本の現行法で可能である。
ところがある日本の法律家が補償金を貰うかわりに裁判を受けさせないというのは訟権に侵害にあたるという解釈をした為、今回の産科医療補償制度では補償金は貰え、克つ訟権を残すという形式になった。法の認識不足である。これでは紛争の終点になっていない。アメリカ形式を採用しなくてはこの制度の意味を成さない。
厚生労働省傘下の調査委員会が事故調査を行い、その調査結果を患者側に公開することになっている。なるほど調査委員会の医学的判定が医師の過失無しの場合なら、補償金は貰い、かつ、過失も無さそうだからとし、あえて訴訟はおこそうとしないだろう。だがこのような症例は紛争になっても医師が勝訴しているはずのものである。問題は調査委員会の判定が過失あり、又は過失の可能性も考えられるとの判定を下したとき、補償金を受けた後でもその調査結果が紛争を誘発する可能性が出てくる。これらが証拠をして採用されるとき医師は極めて不利な立場に立たされることになる。
結局、紛争を防止できそうな事例は極少なく、逆に紛争を誘発する事例が多く出てくるのではないかと危惧するのである。
実質的に強制加入になった
昨年11月5日、厚生労働省は産科医療補償制度未加入なら出産一時金据え置きという決定をした。未加入医療機関で出産した場合38万円でなく35万円しか出さないということである。この制度への医療機関の加入は任意であるのは建前にとなり、開業医はこれに加入せずにはいかなくなった。加入すれば事故調査委員会の調査は強制である。
今後の訴訟は手持ちのカードがすべて公表された状態での戦いとなる。
強制調査を拒否することはできるか
憲法38条「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」、医師であろうとこの法に護られている。この法を楯に厚生労働省からの調査を拒否することは出来る。しかしそうする為にはこの制度から脱会しなくてはならない。また約款により調査を拒否した場合は強制的に脱会させられることになっている。脱会してもまで事故調査委員会の調査を拒むべきだろうか。
我を張らないで、お上を信じてお上の裁定に身を任せなさい。信じて付いて来た者達に悪い目は見させません。そう説き伏せられて、信じて付いて行っていいのかどうか・・・
宗教家は信じることから始まり、哲学者は疑うことから始まる。
厚生労働省と開業医の利害は一致しているか
"事故が起こったとき、看護師に内診させていたことがバレたら罰せられるのでしょうか"という開業医のこの恐れは未だ払拭されていない。厚生労働省医政局看護課長通知は撤回されていないのである。
ここには助産師も雇えないような弱小一人開業医は統合され集約化すればいいという本音が見え隠れしている。この本音があるかぎり、事故が起こったとき開業医は厚生労働省から粗探しされるのは目に見えている。この機会に潰れてくれればこれ幸いであると。
ではどうすればいいか
多分、多分である、自分の患者が35万円しか支給されなくても、この制度外で頑張るべきであろう。またこの制度内で仕事をする場合でもこれを信じきってはいけない。最終的には訴訟の可能性を考えて日医の保険の1億及び損保ジャパンの1億を合わせた計2億の保険を確保していなくてはならない。更にこの訴訟で言う事故発生日はその分娩があった日ではないことを認識していなくてはならない。患者が損害賠償を請求した日が事故発生日となるのである。その損害賠償請求があった時点で保険に入っていなくては保険は利かない。自分がお産を止めても過去のことを考慮し、保険加入を続けて行く必要がある。
開業医から見た産科医療補償制度というタイトルで原稿依頼を受け、更に執筆中に制度未加入なら出産一時金据え置きという厚生労働省の決定を見て、いささか被害妄想的な思考になった。本当は私の予想が当たらなければと願っている。
厚生労働省は平成二十年四月一日より補助金を交付し「院内助産所・助産師外来施設・設備整備事業」の推進を行なっている。院内助産所とは医師が常駐せず、助産師が自らの責任の下に正常な妊娠・分娩を扱う場所である。もちろん異常が起これば病院内にある産科医療施設へ患者を移動する事になっている。平成十四年十一月十四日と平成十六年九月十三日、厚生労働省は助産師のいない産科開業医施設での看護師の内診が保健師助産師看護師法(以下保助看法)違反という見解を示した。それを受けて警察は違反したとする産科開業医の検挙を行なった。その結果、助産師が雇用できない産科開業医は次々と分娩の取り扱いを止めていった。更に平成十九年三月三十日に同省は「看護師は医師又は助産師の指示監督の下診療又は助産の補助を担う」という見解を通知し、看護師と助産師の位置付けを行なった。続いて今回のこの事業である。医療費を可能な限り抑えようとするこの国の方向性が見て取れる。異常のない分娩は医療から切り離す。しかし抑えながら医療の質は落としたくない。ならば切り離しはしたが助産所を医療施設内に置く形式にすれば両方の利点を活かせる。
だが盲点はないだろうか。懸念されるのはこの助産行為が医療から切り離される為、医師の監視下に置かれなくなり分娩監視の法的責任が助産師の手に委ねられる事である。助産師に対する法的な医療管理体制はどうなるか。すでに大学病院でも院内助産所、助産師外来を取り入れているところもある。そうした大学病院を例にとって考えてみよう。教授の責任という立場から見てみる。
大学病院で教授が、
ⅰ 医局員に命じて行わせるのは医療である。
ⅱ 看護師に命じて行わせるのは医療の補助である。
ⅲ では助産師に命じて行わせる業はどの分類に入るか。
①助産師に行わせるのも医療である。
②助産師に行わせるのは医療の補助である。
③助産師に行わせるのは医療でもなく、医療の補助でもない。
①は法的に理論的説明がつけられない。医師免許がないものに医療行為を行わせることはできない。
②は可能である。"医療の補助"の枠を"医療行為"に近寄らせるとすることで解決できる。
③が問題である。医療でもなく、医療の補助でもないというものが存在するか。
存在する。保助看法下で行われる助産行為がそれに該当する。これは医療ではない。
だが、"③医療でもなく、医療の補助でもない業務"となるとそれを教授が命ずるという事自体に法的矛盾が起こる。正にその場所が院内助産所である。例えそれが病院内で行なわれたとしてもそれは教授の管轄外だ。一般病院でも同じ事が言えるだろう。
助産所では、「先生、これは正常分娩ですから、医師は口を出さないで下さい。助産師の責任下で行います」と言う事が罷り通る。困ったことにこれは法的に正当な主張なのである。
カエサルのものはカエサルに返せという聖書の言葉どおり、この業は助産師に返すか。世間が望むならそれも良い。だが病院内でのお産を完全に医療と切り離すことが可能であろうか。血管確保1つにしてもそれは医療である。超音波診断もしかり。残る解決方法は、①助産師に行わせるのも医療である、とする法の拡大解釈である。法を現実社会に適合できるよう柔軟に解釈することもときには必要であろう。
だが平成十四年、平成十六、産科開業医が看護師相手に行なってきた産科医療が違法だと、法を厳格に適用し産科開業医を弾圧してきたのは厚生労働省の方である。その厚生労働省が今度は法を拡大解釈しようとする。話を進める前に産科開業医が犯したとする保助看法違反をもう一度検証してみる。
まず法を見る。
Ⅰ、医師法第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
Ⅱ、保健師助産師看護師法第三条 この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じょく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。
第五条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
第六条 この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師または看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。
第三十条 助産師でない者は、第三条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
第三十一条 看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
二、保健師及び助産師は、前項の規定にかかわらず、第五条に規定する業を行うことができる。
第三十二条 准看護師でない者は、第六条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
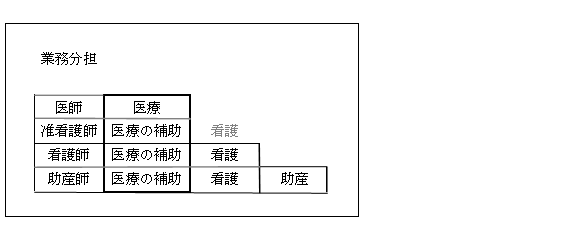
三条と三十条は対になって助産師の業を規定している。五条と三十一条は看護師のそれを、六条と三十二条は准看護師のそれを表すものである。更に三十一条においては助産師に看護師の業を為すことが出来ると定めている。
これから得られる各業種の業務分担は、看護師は自らの判断で行う看護と医師の指示の基で行う医療の補助を行う事ができる。准看護師は看護と医療の補助を行うことができるが、看護については自らの判断で行うものではない。助産師は助産と看護と医療の補助を行う事ができる、となる。
医師は医師法下で助産(正常分娩も)を扱う。助産師は保助看法下で助産を扱う。両者の立脚する法律が異なる。医師法に縛られない、医療として扱われない助産行為が法的に存在する。同様に保助看法に縛られない、医療として扱われる助産も存在する。医療として扱われた助産に保助看法は介入出来ない。それは医療として扱われなかった助産に医師法が介入しないのと同様である。(日本医事新報平成十八年十月十四日号「看護師の内診は違法か」より引用)
よって医療機関内、医師法下で行われた助産に対しこの保助看法違反は成立しない。
またこの法構図を見る限り平成十九年三月三十日の厚生労働省通知「看護師は助産師の指示監督の下に助産の補助を担う」という法解釈が間違いであることが分かる。看護師の業務に保助看法下の助産の補助はない。あるのは医療の補助である。
厚生労働省が平成十四年、十六年と渡って通知を出し、産科開業医から分娩を取り上げる法的意義は無かったのである。
さて今回のこの院内助産所は医師法の通じない場所であるから、ここでの業務に医師は介入できない。助産師の判断がここでの最高意志決定となる。従来の医療の観点から見れば異例の抜擢である。薬剤師が薬を出すには医師の処方箋が要る。放射線技師も医師の指示の下でなければ患者の体に放射線を当てることが出来ない。検査室も同様である。これらすべて法で定まっている。従来の産科医療機関であれば助産師も医師の指示の下で動かなければならなかった。だが今回のこの院内助産所ではこのヒエラルキーが断ち切れる。また患者を院内助産所から病院側に移動する判断も助産師に任せることになる。つまりこの施設においては帝王切開の決定をするのが医師ではなく助産師という事になるのである。
このままこの院内助産所が進化すれば将来次のような助産施設も生まれてくるだろう。それは助産院内産婦人科とでも言おうか。つまりカリスマ助産師の経営する助産所で多数の助産師が働く。その一角に産婦人科医療機関が置かれる。医師はそのカリスマ助産師に雇われた者である。助産師より帝王切開の指示が出れば医師はそれを行なう。ここでは始めから分かっている異常分娩は扱わない。それは総合病院に行ってくれ。ここは健康な妊婦さんがお産をする場所ですと嘯いていればいい。ここでは助産師が扱う正常分娩部門と産婦人科医が扱う帝王切開部門では圧倒的に正常分娩部門の量の方が多い。市場原理主義社会の世の中では多く稼いでいる方の発言力が増すのは当然となる。
庶民には受けるだろう。"健康な妊婦がお産する場所"というキャッチフレーズは妊産婦の耳には心地よく、これがテレビに流れれば民衆は飛び付く。マスコミは怪物を生み出すものである。こうした怪物の台頭を許してはならない。だが院内助産所を国が推進している以上、法的にこうした助産所も認めざるを得なくなる。
産婦人科医不足を院内助産所という姑息的手段で解決しようとすると必ず弊害が起こるであろう。現行法での助産師の業務規定は助産師が医療機関内で業務を行うことを想定していない。想定しているのは医師がいない場所で、医療とは別枠で扱う助産なのである。医療機関内で働く場合には薬剤師や放射線技師と同様に"助産師は医師の指示の下で助産を扱う"といった成文が本来ならなくてはならなかった。
我々が求めている助産師とは*産科医療の*助手を務める*者である。産科医の下で常に技術を修練し産科医療の助けをしてくれる優秀な人材である。医師のいない場所でお産を扱える法的資格は有っても無くてもそれは大した意味を持たない。助産師が名称独占であり、その呼び名が使えなければ、"産科医療助手認定看護師"とでも言えばいい。それは産婦人科学会又は医会あるいは周産期・新生児学会が教育しその認定をすればいいのである。
妊婦検診は助産師外来でなくとも看護師外来であっていい。この認定看護師が超音波等医療検査機械を扱い検診を行なう。患者の希望があれば三十分でも相談に乗って上げればいいのだ。検診の最後に医師がそのデーターに目を通しサインをすればそれで法的にも医学的にも問題はない。こうした優秀な認定看護師の育成に力を注ぐべきなのである。
産科病棟の長は看護大学卒で、NICUや手術室勤務も経験してきた優秀な認定看護師をその師長とし、廻りのコメディカルスタッフを束ねるようにする。それでここは医師を頂点とするピラミッド型の指揮系統に統一される。
この体制は先般、厚生労働省が潰しにかかった産科開業医の形式である。意味のない法解釈によってもたらされた不幸を真摯に受け止め、この国の産科医療形態の構築を図っていかなくてはならない。
忘れてならないのは「医師以外の者に一部の医療を行わせる事によって得られるメリットは医師以外の者の医療行為を禁じた事によってもたらせる福音を上回るものではない」という事実である。
広尾事件と大野事件での告発を契機に医師法二十一条の改正が叫ばれている。山口県医師会報の今月の視点でも「医師法二十一条の改正と医療安全調査会設置法案大網(仮称)」と題して理事の先生より改正の必要性が説明された。広尾事件と大野事件、これは同じ医師法二十一条違反の罪状でも一方は有罪、一方は無罪の判決となった対照的な事例である。平成十六年、広尾事件の際最高裁の下した判決は異状死届けとは「検案して死因等に異状があると認めたときは、そのことを警察署に届け出るもの」であるとし、本件はこれに該当するとした。
一方昨年八月地裁が下した大野事件では医師法二十一条における異状死の趣旨とは「警察官が犯罪捜査の端緒とする、緊急に被害の拡大防止措置を講じるなど社会防衛を図ることを可能とする」とし、本件はこれに該当しないとした。
一般的な見方は、今回無罪になったのだからといって今までの状態でよいとは言えない。これは検察が上告しなかったからそうなったのであって、もし上告し最高裁まで行けば有罪の判決が出たかもしれない。したがって、この最高裁判決を無効化するには医師法二十一条の改正しかない、となる。最高裁まで行けば有罪になったのは確かだと思う。
医師法二十一条の異状死の定義は大きく分けて法医学会の提示した異状死の定義と外科学会が提示した異状死の定義との二つに分かれる。地裁は外科学会寄りの定義を採用し、最高裁は法医学会の寄りの定義を採用した事という事になる。二種類の判決が下されて、今後我々はどちらに従ったらいいのか混乱するばかりである。だからと言ってそれが最高裁判決を無効化しなくてはならない理由になるだろうか。我々は二種類の異なった判決があった事実を率直に受け入れればいいのではないか。一方の定義では異状死に入り届出が要る。また一方の定義では異状死から外れ届出が要らない。そのとき、どちらの定義でも異状死となる症例は届けるのがあたりまえであろう。またどちらの定義でも異状死に入らないのは届けなくていい。問題は一方の定義では異状死に入り、一方の定義ではそれに入らないとなる症例である。だがこれは届ければいいのである。もし本来届ける必要のなかったものを届けてしまっても、何も咎められるものはないのだから。
我々臨床の現場ではこのような事は日常茶飯時であろう。ある疾患の診断に対し二種類の検査をした。二つとも陰性であれば、これはOKを出す。しかし二つのうち一つは陰性だが一つは陽性と出たら、これは癌の疑いがあるとしてその後のフォローを怠らないだろう。こういうファジーな対処には慣れているのである。異状死に関してもどちらかが陽性にでるかもしれないよ、と考えて対処すればいいだけの話である。最高裁を忌み嫌う必要性など何処にもない。
次に厚生労働省が押し進めている医療安全調査委員会設置法案(仮称)大網案について。 この案が通れば、まず医師が検案して犯罪性が疑われれば警察に通報する。その疑いが無ければ警察への通報はせず、調査委員会に委任し、医師の医療過誤が有ったか無かったかを検証する。医師の重大な過誤が認められれば警察に通報となるがそれが無ければ警察への通報はない。こうなった場合検案した医師の社会的責任は重大となる。初動捜査をするしないの判別を行う義務が負わされる事になる。医師にその責任が全う出来るであろうか。
医者より頭のいい犯人がいて、医療事故を装った殺人を犯し、医師は自分の医療行為に間違いは無いと思っていても、死んでしまったのは自然界にはこういう考えられない事態も起こりうるのだろう、勉強になったと、そこでは自分の無過失を証明するのにやっきになり、調査委員会も調査の結果、医療行為に問題は無く医師に過失無しの判定を下したら、それで終わってしまう。この流れ図ではそうなることになる。医師にこの故人にいくらの保険金が掛けてあったかなど知る術もない。善良な医師は人を疑う事など知らないのだ。また医師がどうもおかしいから警察に通報すると言ったら、遺族との間に軋轢が生じるのは目に見ている。医師によほどの自信がないかぎり通報は成されないだろう。通報していたら簡単に発覚した事例が闇に埋もれてしまう可能性がある。こうした事態は社会全体にとって不利益であろう。現行法通り"法により異状死は届けなくてはならないのです"と言う方が医師は楽です。
はじめに
「四禁掟の黄昏」という題名は『紫禁城の黄昏』という本から拝借したものである。この本の著者はイギリス人のR.F. ジョンストン。彼は清朝最後の皇帝溥儀の家庭教師を勤め、溥儀の激動の生涯を記録した。映画にもなった。ベルナルド・ベルトルッチ監督の「ラストエンペラー」(1987)である。映画ではジョンストンの役はピーター・オトールが演じた。禁城とは天子の住む場所という意味で、紫禁城は北京市街の中央に位置する。またこの『紫禁城の黄昏』が極東軍事裁判(東京裁判)に証拠書類として採用されていたら、あのような裁判は成立しなかったであろう、という曰く付きの本である。日本語訳は何冊か出たようだが、それらの本は政治的配慮もあり1 章から10章までと16 章が省かれていた。近年になって全訳が出版され今回通読した次第である。1 つの国が衰亡して行く様を内部に居ながら客観的に記述していて感慨深い。これに触発されたという訳でもないが、私はこの国の産科医療の衰亡して行く姿を四つの掟を通して見てみたいと思う。四つの掟とは厚生労働省によって為された、あるいは為されようとしている①看護師内診問題、②産科医療補償制度、③分娩費直接支払い制度、④医療事故調査委員会大網案の4 つを指す。
掟その1 、看護師内診問題
厚生労働省医政局看護課は「内診行為は、保助看法の第三条で規定する助産であり、助産師または医師以外の者が行ってはならない」との見解を2 度に渡り示した(平成14 年11 月14 日、平成16 年9 月13 日)。これを受けて警察は「看護師の内診は違法だ」との認識のもとに違反医療機関の摘発を行い、摘発を受けた医療機関らは廃業へと陥って行った。さらにその報道を見た産科開業医は続々と分娩を止めて行ったのである。分娩を続けて行こうとして助産師を雇いたくても助産師がいない。弱小開業医は分娩を断念するしか無かった。
だが医師の指示下で行なう看護師の内診は真に保助看法違反に該当するだろうか。
これを検証する為にはまず法を確認しなくてはならない。保健師助産師看護師法は保健師法、助産師法、看護師法の3 つの法を統合したものであると考えることができる。解り易くする為に助産師法という法を1 つの独立した法として取り扱ってみる。医師法と助産師法の対比として見てゆく。
助産師が助産を取り扱っていいという根拠になっている法は
助産師法(保健師助産師看護師)第30 条 助産師でない者は、第3 条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法(昭和23 年法律第201 号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
同法第3 条 この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。
この助産師法の3 条と30 条をもって助産師は助産を行ってよい事になる。
医師は医師法下で分娩を扱い、助産師は助産師法下で分娩を扱う。この両法は"and " ではなく“or " の関係にある。つまり分娩を扱うとき、どちらか一方の法が成立していればいいのである。厚生労働省の言う“助産行為は助産師または医師以外の者が行ってはならない”という表現が全ての誤解を生んだ。正しくは“助産行為は助産師法下または医師法下でなければ行なってはならない”である。
助産師は医療従事者ではない。詭弁のように聞こえるかもしれないが、医師法の枠外で行なわれる助産行為は医療ではない。助産師法下で扱われる助産は人間の正常な生理的現象を取り扱うものである。疾患を治療するという行為は含まれていない。対して柔道整復師や針灸師は極限定された医療行為をする事が法によって許されている。
これは痛みや疾患を治療する行為であるのである。では医療従事者ではない助産師がなぜ医療機関で働いてよいか。それは、保健師助産師看護師法第31 条 看護師でない者は、第5 条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
2 保健師及び助産師は、前項の規定にかかわらず、第5 条に規定する業を行うことができる。
第5 条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
この31 条の2 により助産師は看護師の業を行なう事ができるのである。
当院でも以前は分娩を扱っていた。従業員の中には助産師もいた。私は彼女達を助産師法下の助産師としてではなく、助産の知識を持っている優秀な看護師として扱って来た。彼女達が助産師法下にいたら私には彼女達に命令する権限がないのである。私のコントロール下に置く為には医師法下で働く看護師としてみなくてはならない。私のところでは助産師だけに任せた分娩は無い。すべての分娩に医師が立ち会った。ここには助産師法は存在しない。助産師はいても助産師法下で扱った業務は皆無で、院内の従業員の行為すべてが医師法下に置かれていた。従業員すべてと言っても掃除のおばさんや給食係りは含まない。
医師法下にある医療従事者のみである。医療従事者とは助産の知識を持っている優秀な看護師と一般の看護師である。私は院内の医療従事者すべてに内診を行なわせた。違法性はない。これは看護師に認められている医療の補助としての行為なのである。
法の理解ができていない為、いたる所で不幸が起こった。中型規模の公的病院、産婦人科医は一人二人程度。助産師が足りなくなった。院長は他科の医師である。夜間陣痛発来で入院してきた全ての妊婦の診察を産婦人科医に命じた。お産で起きるのは仕方が無いとしても陣痛発来まで起きて行けとは。その病院の産婦人科は分娩を取り止めた。
掟その2 、産科医療補償制度
平成21 年1 月から厚生労働省主導により産科医療補償制度がスタートした。これによって訴訟なしで障害を持つ子に補償金が支払われる事になった。但し先天異常児は対象外である。「医療崩壊」の著者小林秀樹氏はこうした無過失補償制度が成功する為には次の2 つの要素が不可欠であると述べている。2 つの要素とは第一にこれが紛争の終点となること、第二に当事者の責任の追求とを切り離すこと、の2 点である。日本の産科医療補償制度にはこの両者とも欠如している。お金を受け取る代償として裁判は起こしません、という念書を取る事を禁じた為、今回の産科医療補償制度では補償金は貰え、克つ訟権を残すという形式になった。そしてこの補償制度を通じて厚生労働省傘下の調査委員会が事故調査を行う事にもなった。結果的に当事者の責任追求が行なわれる事になろう。
児に障害が起きた原因追求は純粋に学問的な目で検証しなければならない。そうではなく責任追及に重点をおいて走れば、障害児を出した産科医を粛清して行くのは目に見えている。そして弱小個人開業医は淘汰の方向へ向かうだろう。
今からでも遅くはない厚生労働省は手を引き、この仕事は学会に任すべきである。さらにこの産科医療補償制度には致命的な欠陥がある。それはこの制度の約款第二十七条3 の条文にある、調整委員会が当該重度脳性麻痺について加入分娩機関およびその使用人等における重大な過失を認めたときは、加入分娩機関は、正当な理由がある場合を除き、前条に規定する補償金返還措置を講じなければならない。
である。
これは医療機関に重大な過失ありと調査委員会が判定を下せば患者に支払われたお金は医療機関が返済するという念書である。こんなバカな話はない。過失が有っても無くても支払うという制度だったはずである。この約款第二十七条の3は削除を要請すべきである。そして重ねて言うが、これが紛争の終点となるようにする事と当事者の責任の追求とを切り離す事を盛り込まなくてはならない。
掟その3 、分娩費直接支払い制度
平成21 年10 月1 日より出産一時金直接支払い制度が導入された。先立つ4 月妊婦健診料が市町村持ちになり、この現金収入が月遅れで入るようになったばかりである。一般診療科の先生方にとっては診療報酬が後で入って来るのは当たり前に見えるだろう。しかし産科開業医にとって急に2 ヶ月間の現金収入が無くなる訳である。全国から悲鳴が起こった。貸付金制度も立ち上げられたが結局は借金の利子を今後も払い続けなくてはならない。弱小開業医は淘汰すればいいと言う厚生労働省の思惑が見えてくる。全国の産婦人科の署名運動が起こった。長妻大臣はこの声をくみ上げ完全実施は半年後とした。産科を廃業しようとした人達も一応これで首は繋がった。
しかし患者からは10 月から分娩で支払う金は要らないという約束だったではないか、今になって30万40万の現金を用意しろと言われても、と言う不満が沸いた。医療側と患者側との齟齬が出来てしまった。妊婦健診料は市町村が持つが、分娩費は社会保険と国民健康保険が支払う。妊婦健診料は完全に行政が支払ってくれるので心配ないが、分娩料は基金から出る。分娩時に資格消失者がいて、入院分娩料を貰い損ねたら後になって本人から貰うのは大変な事である。取りはぐれは起こるだろう。更に医療機関と基金とでこんな同意書を交わす事になった。つまり、基金が(自分達の調査不足で)資格消失者の出産育児一時金を間違って医療機関に支払ってしまった時、その後その金を返すという念書である。医療機関の目もすり抜け、基金の目もすり抜け、2 ヶ月遅れで払い込まれたお金を半年後1 年後でも不正が発覚したら医療機関が弁償するという事である。不正が見抜けなかったのは基金側の責任であろう。こうした制度を作るとき、制度を作った役人に責任がかからず、最終責任は末端の医療機関に被せるような文言にしておくのは彼らの常套手段である。経済的に困窮している人々のお産や医療は国が責任を持って面倒みなければならないはずである。分娩時に保険に入っていなかった事が発覚した時、遡って保険に入る手続きをして上げるとか何処からか分娩費を捻出するとかするのは国や基金の仕事である。分娩費用は妊婦健診料と同様、市町村あるいは国持ちにするのがよい。保険に入っているか否かで差別すべきものではない。たとえ税金を一銭も払っていない人でもこの国の憲法で保障する生命及び幸福を追求する権利はあるのだ。
掟その4 、医療事故調査委員会大網案
平成20 年6 月、この大網案が厚生労働省より発表された。医師法21 条の変更である。変更しなくてはならない理由はこの21 条により異状死を警察に届けた医師が業務上過失致死罪で警察からの調査対象になるのを防止する為とある。届け出先を警察ではなく、厚生労働省下の調査委員会にする。調査委員会が事故調査をし、犯罪性があるとしたもののみ警察に届ける。
一見医師にとって警察の追及から救われる朗報のように見えるが、果たしてそうなるであろうか。厚生労働省の真の狙いは医療事故の届けを自省に一括し、医療界全体を我が管理下に置きたいと言う事であろう。今後は厚生労働省による強制捜査に替わるだけである。この委員会の判定に反論する機会が与えられるのだろうか?通常の裁判であればその機会はある。しかし、この判定は弾劾裁判となってしまう危険性がある。厚生労働省の基準で裁く事になるからである。
ではもしこの制度が導入された場合、どういう症例が届出対象になるのか。つまりこの大網案で言う「医療事故死等」という用語の定義はどうなっているのか。
第2 定義
1 この法案において「医療事故死等」とは、第32の(2)の1 の医療事故死等をいう。
第32 の(2)の1 というのは何を指すのかその文章を見てみよう。
第32( 2)病院等の管理者の医療事故死等に関する届出義務等
1 病院若しくは診療所に勤務する医師が死体若しくは妊娠4 月以上の死産児を検案し、又は病院若しくは診療所に勤務する歯科医師が死亡について診断して、(4)の1 の基準に照らして、次の死亡又は死産(以下「医療事故死等」という。)に該当すると認めたときは、その旨を当該病院又は診療所の管理者に報告しなければならない。
では、(4)の1 の基準に該当するとは何であろうか、(4)の1 を見てみる。
(4)の1 、医療事故死等に該当するかどうかの基準○○大臣は、(2)の1 、2 及び4 並びに(3)の1及び2 の報告及び届出を適切にさせるため、医療事故死等に該当するかどうかの基準を定め、これを公表するものとする。
なんと、基準は未だ決まっていないのだ。○○大臣が医療事故死等に該当するかどうかの基準をこれから定めるとある。○○大臣は大岡越前の守にやらせるのか。この大網案を作った人の頭の中はピーマンなのではなかろうか。
基準も決まっていないのに基準に添って届けろと言う。それでいて、届けなかったときの罰則は事細かに厳重に書き込まれている。こんなもの使い物にならない。異状死の定義は法医学会のものが客観的であり、何が異状死として届出対象になるのかあるいは届出の必要がないのかが明白である。
私は現行法通り異状死の定義に入るものは全て警察に届ける、でいいと思っている。異状死を警察に届けず委員会に届けて、委員会が医師に責任が無いと判定すればそれで終わりになってしまう。これではもし犯罪が隠されていた場合、それを見逃す羽目になる。我々には犯罪を見抜く能力が備わっていない。形式的でも全てプロの目を通すべきである。
私はこの21 条の下に但し書きで、
患者の死亡について、その診療に携わった医師は業務上過失致死罪に問われない。
という1 文を付けるだけでいいのではないだろうかと思っている。これは産婦人科学会も提唱している事である。1 億の民が暮らせば年間100万件の死がある。それらの死のまず殆どに医師は関係する。医師は一般の人に比べ死への接触濃度は極端に高い。
一般人同様の業務上過失致死罪を科すのは過酷である。これが免徐されても刑法上の殺人罪は残在するのである。医師が故意に起こしたのならこの罪で起訴する事ができる。警察も医師を起訴するなら、殺人罪をもってこれに当たるべきである。業務上過失致死罪などという安易な法を採用すべきではない。警察が医師の治療が妥当であったか否を判定する任に向かないのは当然である。警察には医療の妥当性を見抜く能力が備わっていない。
私の案が受け入れられる可能性は低いと思われる。しかしこの大網案には産婦人科医として見逃す事が出来ない重大事項がある。それは事故死としてみる対象に12 週以上の流産児を含めた事である。今までの医師法21 条では検案して異状死胎と認めたときであった。つまり外傷があるとか窒息させた痕があるといった嬰児が届けの対象である。今回の大網案は医師が切迫流産の治療をした後、流産してしまった症例もその治療が正しかったか否かの調査対象になる。それもそれを届けなかったら罰則を科すというものである。そして患者側がそう主張すれば強制調査の対象になるのである。何をトチ狂っているのだ、厚生労働省のバカタレが。どこまで産婦人科医を貶めようと言うのか。
結語
4 つの悪しき掟について述べてみた。世界一の水準を誇った我が国の産科医療に衰亡の兆しが見えはじめている。国が衰亡して行くとき、外敵というよりすでに内部からの崩壊が衰亡の要因の多くを占める。衰亡しかけて立ち直った国家もある。 それは彼らが危機感をもったときである。我々も封じ込まれて諦観に陥っていてはならない。危機感を糧に戦わなくてはならない。
上申書
日本産科婦人科学会 理事長 吉村 泰典 殿
―胎児減数手術に関する法的見解ー
胚移植に対してはその移植する胚の数の制限は出来ますが、過排卵刺激ではなお多胎妊娠の可能性は残ります。その為国内で少なからず胎児減数手術が行なわれている現状だと思われます。
倫理的問題は別に考える事としてここでは法的問題について検証してみたいと思います。
死産に法医学が関与する事が有り得るかという問題で、妊婦に中絶を頼まれ妊娠36週の胎児の心臓に塩化カリウムを注射し心停止を起こしてから子宮内胎児死亡として処置をした場合どうなるか、を法医学の医師と話した事が端になります。
日本医師会雑誌134巻第12号平成18年の付録で「医の倫理」ミニ事典という冊子が出ていますが、その中で聖路加病院の佐藤考道先生が「胎児減数手術」についての法解釈で以下のように述べられています。
「人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保持できない時期に、人工的に、胎児及びその付属物を母体外に排出すること」(母体保護法第2条)であるから、減数手術は人工妊娠中絶に当らない。また、刑法第29章には堕胎罪の記載がある。刑法での「堕胎」も「自然の分娩に先立ち、人為的に母体から胎児を分離させること」を言うので、これにも当らない。つまり、我が国には減数手術を規制する法律がない。
これは倫理的問題はあるが法には触れないという考え方です。たぶん生殖医療を行っている医師達もそのような解釈をしていると思われます。
だが、この理論が通ると36週の胎児の心臓に塩化カリウムを注射しても法に触れない事になる。この場合、まだ生まれていないのだから殺人罪には当らない。しかし堕胎の罪は免れようがないでしょう。刑法の文章には殺人罪、傷害罪という用語の定義はありません。同様に堕胎罪という用語の定義も刑法の文章の中にない。そういう用語は常用語として使用されているからその定義までは書く必要がない。これは子をおろすという意味になるのだと思います。現に大辞泉で「堕胎罪」を引くと"胎児を母体内で殺し、または早産させる罪"となっています。私は9週の胎児でも母体保護法下による減数手術でなければ刑法上の堕胎罪は成立するのではないかと思っているのです。
確かに母体保護法の文面では減数手術は人工妊娠中絶に該当しない。しかし母体保護法を満足させないという事が堕胎罪を免れる理由にならない。
もし裁判になれば法律家はそのような裁定を下す可能性は極めて高いと思われます。
あまり四角四面に物事を捉えるのもどうかと思うのですが、揚げ足を取られないように法の手続きを踏んで置くに越した事はない。若い医師を法の手から守る為にも万全の策を立てて置く意味はあると思います。愛媛玉ぐし料訴訟や北海道空知太神社訴訟の事例からも見られるように当事者は当然の事として行っている行為であっても法に照らし合わせてみてば違法という判断を裁判所が下す場合もあるのですから。
では母体保護法を適用するにはどうしたらいいか。文面通りに適用するのでなく、母体保護法の拡大解釈でいいのではないかと思います。我々も現状では母体保護法を拡大解釈して本人希望の中絶なのに母体を護る為と称してこれを適用している。むしろ減数手術の方が母体の身を考えてという意味でこの法の精神に合致していると言えます。
全員が母体保護法下で減数手術を行なうとなれば、代理懐胎など規律違反をする医師は学会追放だけでなく母体保護法指定医の剥奪もしてしまえば、その医師が中絶手術や減数手術を行なったことが発覚すれば刑事訴追することも可能になる訳です。
平成22年1月29日
(母体保護法の指定権について)
厚生労働省は母体保護法の指定権限は公益法人である都道府県医師会に委譲するが、一般法人である都道府県医師会には委譲しないと決めた。
公益法人になれない県は母体保護法指定医の認定権を取り上げられ、その指定権限は厚生労働省に行くというシナリオが考えられる。
それは具合が悪い。なぜ厚生労働省に行ってはまずいか。
指定医本人に対する認可、施設に対する認可、これは厚生労働省が行なっても問題ない。問題は手術の適用である。これを法どおりにやりなさいと言われたらどうしようもなくなる。
私はこの法自体に欠陥があると見ています。本来ならこの法はこういう文面でなくてはならない。「中絶手術はこれを行ってはならない。ただし指定医が認めた場合はその限りではない」となっていればいい。こう明確に指定医の裁量権を認めているのならいい。これなら別に厚生労働省が管理しても問題ない。
しかし、実際の母体保護法の文面は「~~、~~の理由によりこの妊娠の継続が母体の健康を著しく害するおそれがあるもの」となっており、これは医学的適用のみで社会的適用を認めていないのです。だが現状は病気の妊婦のみだけでなく健康な妊婦の正常な妊娠も行なわれているし、それが求められている。
つまり①社会的適用で手術をしてやってくれ。②ただし法は厳守しろ。これは全く矛盾した要求を指定医に課していることになります。
これは産婦人科医である保護法認定委員会が産婦人科医の会員に対し「中絶の適用は厳密に守って下さいね」と言っているから成立している。阿吽の呼吸です。認定委員会と指定医はこの法の欠陥を補う関係であります。
この法の管理者が厚生労働省に行くと、具体的にはその地の保険所長になると思われますが、彼に「厳密に法を施行せよ」と言われると現時点で我々の行なっているほとんどの症例が違法中絶と解されます。
県医師会でも医会でも学会でもいい管理者の実体は産婦人科医であることが必要です。
この事は他科の医師に言っても理解してもらえない。産婦人科のエゴととらえられるだけです。
また欠陥のある法だからこれを破ってもかまわないというこの主張は世間には通用しない。
もしこの法の管理が厚生労働省に行くなら、法を「ただし指定医が認めた場合はその限りではない」と書き換えて貰わなくては我々はこの仕事が出来ない。
しかし、法を書き換えて自由にこの手術が行われるようになるのはよくない。現状のままがいいのです。この手術を受ける者もこの手術を行う者も、これは違法な事をしているのではないかという後ろめたさを感じる。
この後ろめたさがこの手術の抑止力になっている。「女性には中絶を受ける権利がある」と声高々に主張するような風潮は抑えるべきです。この国では堕胎は法で禁じられているという事が前提になっている必要がある。
さてこの母体保護法(旧優性保護法)が制定されたのは昭和23年、日本が占領下の時代です。GHQは優性を保護する、言い換えれば劣勢は排除するというこの法を日本政府に任せるのは危ないと考えたのでしょう。そして医師会に任せた。GHQの判断は正しかった。それ以後この法はこの国で何の問題もおこらず適用され今に至っている。当時、産婦人科医会は存在していなかった。存在していたら医会が引き受けていてよかったのではないかと思います。そう考えれば、今日この時点で、県医師会から医会支部に移っても不自然なことではない。
医会本部は議員に働きかけ、法を改正して日医がその権限を持つようにしようとお考えのようですが、そんな事をしていたら時間切れになる。法を書き換える必要はない。現行のままで行けます。
厚生労働省は現状の適用上で何も問題がないにもかかわらず、法の言葉の綾を取ってこの権限を取り上げようとしている。「公益法人である」という文章をもとの「社団法人である」に戻すことも禁じた。ゴリ押しです。理不尽なやり方で怒りを覚えます。むこうがそのような手段で来るなら、こちらも同様な言葉の綾で対抗処置をとるまでです。
以下私の案を示します。
①医会支部が公益法人化する。本部はなってもならなくてもいい。
②支部の名称を○○県第2医師会と名乗る。
③そ指定権限を○○県医師会から○○県第2医師会(旧名称、医会支部)に移譲する。
これは全国統一して行なわなければならない。医会本部が信頼できる税理事務所に定款の雛形を作らせ、それを各支部に配布する。そして全都道府県に公益法人化した第2医師会を置く。
これで法を変えずに対処できます。